概要
令和7年第3回定例会は、16日間の会期(6月10日~25日)で開かれました。
本定例会では、4つの特別委員会の委員を選任し、一般会計・特別会計の補正予算などの議案18件を原案のとおり可決しました。
一般質問
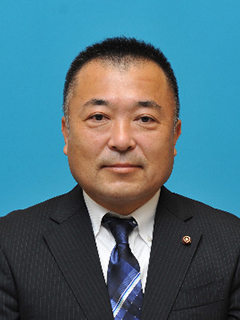
令和の米騒動、本市における傾向と対策について
質疑
本市における米の需要と供給についての課題は。
答弁
昨今の米価高騰の状況を鑑みると、全国的な需給バランスが今までと違う状況にあると考える。また、今年度は飼料用からの転換で主食用米が大きく増加見込みである。国では、米価高騰の要因分析、生産調整の見直し、所得補償の新設などの検討を開始した。本市も状況を注視したい。
質疑
中川ライスセンターが老朽化により今年の秋で閉鎖すると聞く。小規模農家にとっては非常に重要な組織である農協の施設の老朽化を本市はどう把握しているのか。
答弁
ライスセンターなどの施設は、昭和50年代から平成の初めに建設され、建設から相当な年数が経過している。JAには計画的な修繕など、適切な維持管理に努めていただくとともに、本市も稼働や利用状況の把握に努めていく。


平和事業と平和教育について
質疑
今年は戦後80年の節目の年である。戦争関連の遺品を市が預かり、展示公開する事業を検討できないか。遺品を通じて平和の尊さを学べると考えるが、本市の見解は。
答弁
戦争関連の遺品は、ご遺族 遺族に保管していただくことが適切と考える。昨年、遺族の会主催による特攻隊員の遺品展示等を行い、好評を得た。今後も引き続き遺族の会等と連携し、戦争関連遺品の意義や歴史的価値を広く伝える努力を重ねていきたい。
道路交通法改正に伴う市の安全対策の考えについて
質疑
自転車の右側通行や歩道通行は、罰則の対象となるが、通行可の歩道もあり、分かりづらい。歩道などに対策が必要だが、本市の考えは。
答弁
自転車は歩道の有無などで通行帯が異なることから、誰もが分かりやすく安全に利用できる通行空間を確保できるよう、警察をはじめ関係機関とも連携し取り組みたい。


カスタマーハラスメント防止の取り組みについて
質疑
カスタマーハラスメントに係る実効性の高い条例を本市で制定する考えは。
答弁
カスタマーハラスメントから労働者を保護するため、本年6月に改正労働施策総合推進法が可決・成立し、県では、カスタマーハラスメント防止条例が本年4月に施行されたところである。本市においては、これらの動向を注視しながら、カスタマーハラスメント防止に資する全般的な対策を検討していきたい。
町内会活動の負担軽減ついて
質疑
町内会への支援を強化するため、専門的な担当課を設置する考えは。
答弁
町内会は地域活動の中心的な団体で、その運営においては少子高齢化、価値観の変化などを背景に多くの課題があることは認識している。町内会への支援については、一元的に企画調整課が所管しており、今後も同課で対応していくものと考えている。


市民の思いと地方自治体の役割について
質疑
政策実現において法令整備や国・県の通達を待たずに地方自治体の考えや意識で改革できるものがあると考える。役割をどう捉えているか。
答弁
施策や事業の内容により取り組み方法は異なるが、本市が全国に先駆けて実施したヤングケアラーSOS事業は国を巻き込んだ取り組みに拡大した例である。
スピード感を持って真に必要な事業を実施することが、自治体の役割の一つと考えている。
横断歩道橋の安全対策と今後について
質疑
交通安全上重要な施設である横断歩道橋の老朽化等への対策と今後の在り方は。
答弁
歩道橋は交通安全上必要性の高い施設だが、一部には経年劣化が見られる。存続に当たりバリアフリー化や維持管理費用等の課題もあるが、利用者の安全を確保するため、必要な補修をし、新技術活用の検討やコスト縮減を図り適正な維持管理に努めていく。


交通施設の整備について
質疑
長年にわたって交通渋滞の緩和が図られない交差点があるが、本市の取り組みは。
答弁
交通量の多い国道や県道の一部の交差点では、右折車線などが整備されていないことから渋滞が発生していることは認識している。交差点改良は用地買収が伴うため、交渉などで相当の時間を要することとなる。本市としては、今後も道路管理者である国や県に対して、道路の拡幅や交差点改良などの要望を継続的に行い、交差点の交通渋滞緩和に向け取り組んでいく。
高崎スマートIC産業団地パーク型商業施設について
質疑
公共性が高いことを理由としたパーク型商業施設への支援をいつまで行うのか。
答弁
当該施設は、市民をはじめ来場者のにぎわいと交流の拠点となる公共性の高い施設であり、防災面での特性もある。5年間をめどに支援し、それ以降は、施設の運営状況により協議する方針である。


森林環境譲与税について
質疑
森林環境譲与税のうち、市町村に使途が委ねられている森林の整備の促進に関する施策への活用状況は。
答弁
本市では、観音山自然歩道の整備や吉井地域の牛伏山を花で囲むプロジェクト、群馬地域での古墳の木製階段の改修、くらぶちメロン村における水耕栽培ハウスへの木質バイオマスボイラーの導入などの森林、木材の魅力を引き出す事業に活用している。
感染症とワクチン接種について
質疑
百日せきによる乳幼児の重症化を防ぐワクチン追加接種に対する助成が必要と考えるが、本市での助成は。
答弁
日本小児科学会では、ワクチンの効果が弱まるとされる学童期前と11~12歳の間の追加接種を推奨しているが、全国的に追加接種への助成を行う自治体は少なく、本市も助成は行っていない。今後の国の動向や他の自治体の導入状況等を注視していく。


